先日、新聞をペラペラとめくっていたら、「就職氷河期世代を支援します!」といった、前向きで力強いメッセージの広告が目に飛び込んできました。
希望にあふれたビジュアルで、「未来は明るいぜ!」みたいな感じのポスターです。
私もね。一瞬、「おぉ、かけ声じゃなくて、いよいよ本腰を入れてくれるんですか!」と感動しかけたんですけど、いやいや、ちょっと待ってくださいよ。
そろそろ、参議院議員選挙が近づいていますよね?
政府与党や野党が声をそろえたように叫ぶのは、もしかして、そのための「ポーズ」なんじゃないんですか?
ひねくれ者の私は、そんなことを考えてしまったんですよ。
「氷河期世代支援」って、確かに聞こえはいい。
でも、氷河期世代で苦しんでる人の本当の気持ち、どこまでわかってくれてるんだろう?
 シモ
シモ上っ面の支援だけじゃ、この長年こびりついたモヤモヤは晴れないんですよ!って、机を叩きながら声を大にして言いたいんです。私。
そこで今回は、氷河期世代からやむを得ずフリーランスに転身した私が、氷河期世代支援の全体像や方向性、そのギャップなどについて、解説したいと思います!
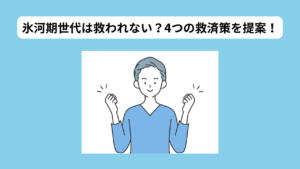
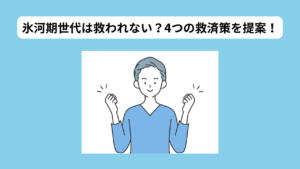
氷河期世代が抱える、綺麗事じゃ乗り越えられない心の闇


この就職氷河期支援の広告を作った担当者さんは、私たち氷河期世代の心の内を本当に理解しているんでしょうか?
私たち氷河期世代は、長年の不遇で心に深い傷と複雑な感情が刻まれています。
このたまりにたまった不信感は、ここまで来てしまうと、ちょっとやそっとじゃ晴れません。
例え、どんなに良い支援制度があったとしても、私たちが二の足を踏んでしまう最大の理由なんですよ!
いまさら「応援します」と言われても…
氷河期世代の多くは冷遇され続けてきたので、「再チャレンジを応援します!」などと甘い言葉をささやかれても、もはや響きません。
長引く非正規雇用や社会からの疎外感により、とっくのとうに将来への希望なんて見失っているんですよ!



選挙が近づいてきたからって、与党と野党そろって、氷河期世代支援を言い始めるのはおかしいだろー



今さら氷河期世代の支援策を拡充するより、社会保障の負担を減らして使えるお金を増やしてもらった方がいい



制度だけ整えても、多くの企業に届いてなければ意味がない
まずはこの心理に寄り添い、細やかなアプローチが不可欠だと私は思うんですよねー。
どうせ支援と言っているだけでしょ?社会に対する不信感
氷河期世代のなかには、社会に対して強い不信感を抱いている人が数多くいます。
特に、人間不信や深い孤立感、他世代への複雑な感情は計り知れないことでしょう。
新卒時の就職活動での挫折や長い非正規雇用経験から社会に対する期待感が薄れ、あきらめにも似た心境になってしまっているんですよ。
支援窓口を訪れたところで、
「どうせ事務的な対応しかされない」「自分の状況を理解してもらえない」といった心理になり、結局は足が遠のいてしまうケースもたびたび見られます。
なので、ちょっとやそっとの支援じゃー、もう、納得しないレベルにまで到達してしまったんですよ。就職氷河期世代は!
もう、いいよ…。長年の不遇が招いた、支援への複雑な心理
就職氷河期世代は、当時から支援を必要としてきたものの、ないがしろにされてきた苦い経験があります。
その苦い経験から、いまさらの支援に複雑な感情や抵抗を抱いているのではないでしょうか。
長年の不遇や社会からの冷遇により、支援策を疑う気持ちや、あきらめが先行してしまうのです。
そんな状況なので、「自分自身の問題を今さら打ち明けろと言われてもね」と抵抗したくなるんですよ。
つまり、過去に期待を裏切られ続けられた就職氷河期世代からすれば、「さんざん訴えてきましたけど…」。
と、言いたくもなるってわけです。
結果、新たな支援に対しても疑う態度を取らせているのです。
ここまで来ると、問題は根深いですよ。ほんとに。
現在の就職氷河期世代支援制度 形だけは整ってるように見えるけど中身は?


就職氷河期世代支援には、国や自治体レベルでさまざまな取り組みが実施されているようですが、本当にそれらが私たちの希望するものなのか、疑問符がつくことも少なくありません。
氷河期世代の支援制度を考えた政府と当事者の間には、大きな隔たりがあるんじゃないか?
それが、「応援します!って声高に叫ばれてもねー」との氷河期世代の声に反映されている気がするんですよ!
国レベルでの支援体制:ハローワークの専門窓口、本当に機能してる?
国レベルでの就職氷河期世代の支援体制は、一見整っているように見えます。
ハローワークの専門窓口やハロートレーニング制度の活用、地域若者サポートステーションなどなど…。
でも、それらの支援は当事者のニーズに本当に合っているんですかねー?
これらの支援は、画一的な運用になってやしないかと、私は思うんですよ。
多くの氷河期世代も私と同じように、新しい支援体制に「今さら感」をもっていることでしょう。
「仕事を選ばなければいくらでもある。」といった、ありがちな対応ですね。
こんな対応をされたら、「結局何も変わらない」と感じて、相談することすら馬鹿らしくなりますよ!
就職氷河期世代支援をするなら、形式的なものでなく、個々の抱える複雑な背景を深く理解して、心理面にも配慮した柔軟な対応が必要ですよね。
それには、人材育成と体制強化が急務だと個人的には思うんですよ。
そもそも、ハローワークの職員さん自体が非正規で働いていたり、雇い止めにあったりというブラックジョークのような現実もなんとかすべきですよ。
一体どうなってるんだ???
自治体レベルでの支援事例:神奈川、千葉の例。本当に就職氷河期世代の「心」に寄り添えてる?
自治体レベルでも就職氷河期世代への支援が展開されています。
例えば、東京や神奈川は以下の通りです。
【東京都】
| ・就活エクスプレス(早期就職支援を目指す方対象) ・東京仕事塾(2カ月間の職務実習) ・Jobトライ(企業内実習でスキルや経験を活かせるかを見極める) ・東京ミドルワークチャレンジ(働くことを通じて自立を目指す) ・デジタル・ビジネススキル習得支援事業(プログラミング言語を使用しないプログラミング開発手法などの習得) ※いずれも東京仕事センターでの支援事業 |
【神奈川県】
| ・かながわ若者就職支援センター(ジョブカフェ) ・シニア・ジョブスタイル・かながわ川崎市就業支援室(キャリアサポート川崎) ・相模原市総合就職支援センターFプレイス就労支援・資格取得講座 ・「働き方相談室」ひきこもり地域支援センター(横浜市・川崎市・相模原市・鎌倉市) |
「これらの施設が本当に必要としている人に有益な支援なのか」「実際に働いてみて、教育プログラムが通用するものなのか」は、不透明です。
例えばですよ。
東京都のデジタル・ビジネススキル習得支援事業は、最短で2週間、短期習得で1カ月のコースとなっています。
これだけの短い期間で、仕事で実践的な技術を身につけられるわけがないと思うのは私だけでしょうか?
そもそも、就職氷河期世代の方は、自分の希望に添わない仕事に就いていたとしても、正社員や派遣社員などの就業経験を通じて、一般的なITスキルは自然に身についているわけですからね。
何かズレてる気がするんですよ。
ちなみに私は、40代前半の時に、東京都のある就労支援制度を利用したことがあります。
その就労支援は、履歴書の書き方、自己アピールの仕方、簡単なITスキルなどを学ぶ内容でした。
私が希望する仕事は、編集・ライター職。
それでも、やるべきだと背中を押されて参加してみたものの、ズレた支援でした。
結局、紹介されたのは、倉庫業や施工管理などの希望とかけ離れた分野の仕事しか紹介されなかったんですよね。
でも、ちょうどその頃は、結婚して間もなかったこともあり、「とにかく職を得なければ」との焦りから、担当者のすすめるままに給料の良い会社を選んでしまいました。
それが、失敗だと思ったのに気づくのは、そう遅くはありませんでした…。
正社員として入ったものの、実態は他の企業に常駐して働く派遣社員のように働く「名ばかり正社員」だったんです。
結果、上司のパワハラや希薄な人間関係、かけ離れた分野の仕事ということもあり、1年ほどの短期間で退職してしまいました。
その頃は、40代中盤だったんですが、就職氷河期世代が体験する「新卒時の雇用のミスマッチからの退職」が、この期におよんでも繰り返されたことになります。
つまり、就職氷河期世代の支援は、その人に合った方法ですすめていかなければ、ズレたまま進むだけだということですよ。
政府が新たに打ち出した3つの就職氷河期世代支援方針には、やはり、いまさら感が…。


政府は今年6月の「就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議」で、新たに就職氷河期世代支援の3本柱を決定しました。
3本柱の内容は、以下の通り。
| ・「就労・処遇改善に向けた支援」 ・居場所作りなどの「社会参加に向けた段階的支援」 ・家計改善・資産形成支援などの「高齢期を見据えた支援」 |
これら3つの柱は表面的にはもっともらしく見えますが、本当にうまく進むものなんでしょうか?
この章では、就職氷河期世代支援の3本柱について一つ一つ解説します。
①「就労・処遇改善に向けた支援」
政府が2025年6月に発表した氷河期世代へのキャリア形成の支援項目で、「就労を受け入れる事業者の支援」があります。
「就職が困難な就職氷河期世代の求職者を無期限で働けるようにする」というものです。
トライアル雇用で雇い入れてくれる事業主に助成金を支払い、氷河期世代の雇用を拡大させていく狙いのようなんですが、実行は2026年を予定しているとのこと。
就職氷河期世代の中には、今この瞬間にも生活に困っている人がいるというのに、来年から?トライアル?
そんなのんびりとしたことを言ってる場合じゃないと思うんですよね。
ちなみに、この認定就労訓練事業を担う事業者の一覧を見てみました。
例えば、神奈川と千葉です。
認定就労訓練ができる事業の分野は、デイサービスや清掃、警備や農作物の出荷作業など、限られた仕事しかありませんでした。
これらの仕事は、大事な仕事です。
「でも、もうちょっと職業の幅はないの?」と思ってしまいます。
SNSでは、こんな意見がありました。
まさにその通りですよね。
②リ・スキリング:「勉強より就職させて」
就労・処遇改善支援のなかでは、リ・スキング(学び直し)の支援も進めていくようです。
計画では、非正規雇用の人たちが働きながら受講しやすいオンラインの職業訓練を2026年から全国化すると書いてあります。
でも、この中身も先述の就労支援のように、限られた訓練しかできないんじゃないだろうか?
そんな疑問もふつふつと湧き起こってくるのは私だけでしょうか?
というわけで、キャリアアップ支援事業者の一覧も調べてみました。
| ・プログラミングスクール ・キャリア支援スクール ・介護職 ・ITエンジニア ・Webデザイン・グラフィックデザイン ・AIプログラミング ・動画製作 |
これらのスクールは、今どきの分野が含まれていますけど、これってどれくらいの期間受けられるものなんでしょう?
詳しく見てみると、最短1カ月なんて書いてあるプログラムもありましたが、いやいやいや。
そんな短い期間で何を学べるんだと。
「やることだけやってます」との政府のアピールと、助成金をもらうスクールが潤うように思えてしまうのは私だけでしょうか?
就職させてもらったうえで、継続して勉強させてくれるならまだしも、短期間で何が身につくのかと。
ほんとに就職氷河期世代に寄り添ってます?これって。
SNSの意見では、このような冷めた意見が、見られます。
③居場所作りなどの「社会参加に向けた段階的支援」。 段階的?そんな悠長なこと言ってられない
政府による社会参加に向けた段階的支援では、就職氷河期世代で引きこもりになってしまった人に対する支援プログラムを充実させるとのことです。
具体的な内容は、以下の通りです。
| ・社会とのつながり確保 ・支援就労に困難を抱える人の職業的自立に向けた支援 ・柔軟な就労支援の確保 |
この支援は、「2026年度から氷河期等交付金で当事者同士の交流の場の設定、支援団体の活動の後押しなどを行う」とあります。
でも、当事者同士の交流の場を設けるのはいいんですけど、それから先どうするというのが見えてきませんね。
個人的には、「わざわざ政府の後押しで交流しなくても、別の場所でつながれるよ」と思うんですよねー。
また、政府は、就労に困難を抱える人の職業自立に向けた支援も行うそうです。
具体的には、就職氷河期世代専門の担当者が付いて、「自己理解」「応募書類の作り方」を継続的にサポート。
人によっては、特別養護老人ホームや児童福祉施設などでの掃除や事務作業なども体験できるようです。
ここでまた疑問がわいてきます。
「いまさら、自己理解や応募書類の作り方を教えてもらうの?」「自分が希望する職種とはほど遠い職種で働くことになるんじゃない?」と。
例え、職を得られたとしても、長続きしないような仕事なら意味がない。
就職氷河期世代の中には、自分が希望した仕事に就けずに、本意ではない職種に就いて挫折して転職を繰り返したり、派遣に甘んじたりという結果になっている人も多いんですからね。
ここでまた、雇用のミスマッチを生んでしまうと、「またか…」と、深い傷が刻まれるだけなんじゃないか?と私は思うんです。
受け入れ体制を広くしている企業だって、限られている気がしてならないんです。
と冷めた声が挙がっています。
④高齢期を見据えた支援?物価高の今の世の中で、支援できるでしょうか?
政府が発表した氷河期世代支援の支援の中には、高齢期を見据えた支援というものもあります。
具体的には以下のような内容です。
| ・就業機会の確保家計改善 ・資産形成の支援住宅確保の支援 |
就業機会の確保では、70歳までの就業機会を保障する企業に助成金を与えることが検討されているようです。
でも、働く側からしたら70歳まで働くというのもなかなかですよ。
自分がやりたいと思える仕事ならまだしも、掃除や重労働だったら、厳しくて辛いだけです。
家計改善・資産形成の支援に関しては、具体的な中身がないのでよくわかりません。
家計改善や資産形成といわれても、現在の物価高で、家計改善はできそうもないし、資産形成の余裕などないのに、何をやればいいのかと感じてしまいます。
住宅支援に関しては、2025年に施行を予定している「改正住宅セーフティネット法」により、住まいの確保が難しい方に、住宅の確保や経済的援助などを行うとのことです。
でも、これだって家があっても、職がなければ話になりませんよね。
まとめ:選挙が終わったら終わりでは困る。就職氷河期世代の問題は一向に改善しないんだ!
「就職氷河期世代支援」のような言葉が、選挙のたびに流行語みたいになるのはもううんざりです。
大切なのは、選挙が終わっても、その場しのぎじゃなく、私たちの心に寄り添った長期的な支援を継続すること。
「制度を充実させるだけでなく、私たちが抱える心理的な壁を理解して、それを乗り越えるための具体的なアプローチに落とし込んでほしい」。「何よりも、当事者の声をしっかりと反映させてほしい」。
私たちの立場を理解しない、「上から目線」の支援は、もういらないんですよ。
社会全体で、この世代が抱える問題への理解を深め、本当の意味での「再チャレンジ」を応援してくれるような社会になることを、切に願います。
にほんブログ村


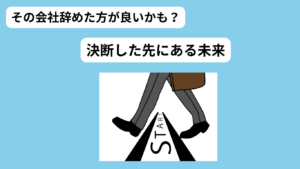


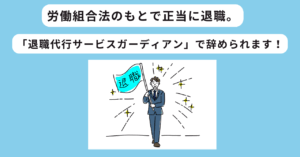
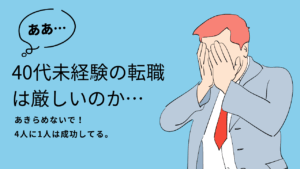
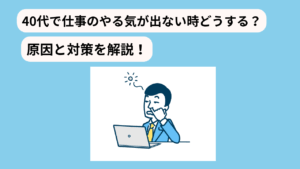
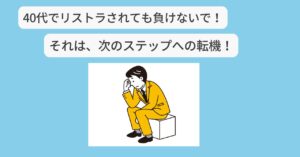


コメント