
「Webライティングのスキルを上げたいけれど、何から始めればいいか分からない…」



「忙しくてなかなか時間を取れない…」
もしあなたがそう感じているなら、今日から「写経(しゃきょう)」を始めてみませんか?
写経と聞くと、お寺で行うお経の書き写しを想像したりしませんか?
いやいや、違います。
Webライティングにおける写経は、「優れた文章を書き写し、その文章構造や表現方法、書き手の意図を徹底的に学ぶ」ことを意味します。



実は写経って、多くのプロのWebライターやコピーライターが実践している文章力向上のためのトレーニング方法だったりするんですよ。
今回は、フリーランスのwebライター5年目の私も実践しているWebライティングの写経の基本から、「10分写経」の具体的な方法、写経で得たスキルを最大限に活かすための応用テクニックまで、徹底的に解説します。
さあ、今日からあなたも私とともに文章力を次のレベルへと引き上げましょう。
- Webライターが写経を行うメリット
- 写経前に知っておくとよいwebライターの基本的な文章テクニック
- 10分写経の進め方
- 写経で得たスキルを次に生かす方法
Webライティングにおける写経の5つのメリット


Webライターが文章力を高めるうえで、「写経」は非常に効果的なトレーニングです。
私の個人的な考えですが、写経は長年自分自身に身についてしまった書き方のクセや思考法に新たな視点を得られる「気づかせ屋」のような役割をもつものだと思います。
冒頭でも触れた通り、Webライティングにおける写経は単に文字を書き写すだけの行為ではありません。
その本質は、「模倣(まね)から学ぶ」という点にあります。
この章では、webライティングにおける写経の5つのメリットについて紹介します。
メリット①優れた文章の「型」を身体で覚えられる
読者に伝わりやすい文章には、共通の構成や論理展開の型があります。
写経を通じて、これらの「型」を意識的にインプットすることで、自然とあなたの文章にもその型が身についていくでしょう。
読者が「スッと頭に入る」「納得できる」と感じる文章は、型に基づいています。
型を覚えることで、あなたの記事も読者にストレスなく読んでもらえるようになるでしょう。
メリット②表現の引き出しを増やせる
同じ内容でも、書き手によって表現の仕方は人それぞれです。
写経を通して多様な言い回しや語彙に触れることで、あなたの文章の表現の幅が格段に広がります。
私は、ある映画の記事を写経していた時に、「この映画をこんな視点で書くのか?うわー、やられたー、これは革命だ!」
と、部屋の中でもんどり打ったことがあります。
こういう文章に出会えるのも、写経の醍醐味です。
メリット③書き手の意図や読者への配慮を読み解ける
「なぜこの言葉が使われているのか?」
「なぜこの順番で情報が提示されているのか?」
表面的な文章の書き方だけでなく、その裏にある書き手の思考や読者への配慮を読み解くことができるのも、写経の魅力です。
優れた文章の裏側にある「意図」を読み解くことにより、読者の疑問を先回りして行動を促す文章を書く力が養われます。
メリット④「書いていないこと」を想像できる
優れた文章は、言葉の選び方や構成だけでなく、感情に訴えかけるような「見えない工夫」が隠されています。
写経する際には、文章の奥にある、書き手の思いや意図を想像することで大きな学びとなるでしょう。
ただ書き写すだけでなく、この「想像する」という意識を持って写経を行うだけでも、のちのちライターとして「読者の心に響く表現」ができるようになるはずです。
メリット⑤タイピング速度と正確性が向上する
写経は、文章を読みながら正確にタイピングをする練習でもあります。
継続することで自然とブラインドタッチの速度が上がり、結果的に執筆スピードの向上につながります。
つまり、写経は、文章スピードと文章力向上の一石二鳥の効果を得られるというわけです。
写経をする際は、時間を決めて行うといいかもしれません。
「その時間までに終えなければ」との意識が働き、ライティングスピードが上がるようになりますよ。
10分写経をより効果的にするために。Webライティングの基本的なテクニックを知る


写経の効果を最大限に引き出すためには、文章の「型」や「読みやすさ」といった基本的なテクニックを事前に知っておくこととより効果を発揮できます。
これらの知識があれば、写経中に「なぜこの文章が読者に響くのか」といった本質的な気づきも格段に増えることでしょう。
この章では、Webライティングの基礎力向上テクニックについて取り上げます。
読みやすい文章の6つのコツとは?
どんなに良い内容でも、読みにくい文章では読者が離れてしまいます。
以下のポイントを意識して、読みやすい文章を目指しましょう。
【読みやすい文章の6つのコツ】
コツ①1文は60文字以内にする
一文が長すぎると、読者は途中で読むのをやめてしまいます。句読点も活用し、簡潔な文章を心がけましょう。
コツ②主語と述語のねじれをなくす
特に長い文章になると、「誰が(何が)どうした」という対応関係が崩れがちです。文章を書く際には、文章のねじれに注意しましょう。
コツ③口語表現を適度に使う
Web記事は、論文や専門書のように堅苦しくする必要はありません。読者に語りかけるような口語表現を適度に使うことで、親しみやすく、読みやすい文章になります。
コツ④「てにをは」を意識する
助詞の使い方は、文章の自然さや意味の正確さに直結します。「てにをは」が適切でないと、非常に読みにくい文章になってしまいます。「てにをは」には、注意しましょう。
自分の書いた文章を声に出して読むと、おかしなところに気付くことがありますよ。
コツ⑤同じ文末表現を使いまわさない
「〜です。〜です。~です。」と続くと、単調で幼稚な印象を与えます。「〜ます」「〜でしょう」「〜ました」など、文末にさまざまなバリエーションを付けて使いこなしましょう。
コツ⑥漢字とひらがなの割合を3:7にする
漢字が多すぎると、読みにくく堅苦しい印象を与えます。ひらがなを多くすることで、柔らかく、親しみやすい文章になります。
写経する際も、これらの6つのテクニックを確認しながら分析してみてください。
読者に「伝わる」文章の型を活用する
Webライティングにおいて、論理的に分かりやすい文章を書くことは必須です。
とはいえ、論理的に書くと言ってもどうすればいいのかわかりませんよね?
そこで、型を用います。
型を用いることで、論理的な文章を書く手助けになりますし、文章を書くのに迷わなくなりますよ。
次の節で、3つの型を詳しく見ていきます。
①PREP法
論理的な文章を書くのに、代表的な型の1つに「PREP法」(Point-Reason-Example-Point)があります。
プレップ法は、説得力のある文章を書く際に非常に役立つ手法です。
具体的には、以下のような方法で記述します。
Point(結論):最初に結論を述べる
Reason(理由):その結論に至った理由を説明する
Example(具体例):具体的な例やデータを示す
Point(結論):もう一度結論を強調する
PREP法で書いた記事は、例えば、このような感じです。
写経する際にも、PREP法を意識して写してみてくださいね。
②SDS法
論理的な文章を書く2つめの型に、SDS法があります。
「最初に要点を伝え、次に詳細を説明、最後に再び要点を述べる」といった流れで書くので、読み手は話の流れを理解しやすく、書き手は伝えたい内容をより深く記憶に留められます。
具体的には、以下のような方法で記述します。
Summary(結論):文章のはじめに結論を述べる
Detail(詳細):具体的な説明や例を挙げる
Summary(まとめ):もう一度結論を繰り返す
SDS法を使って書く文章は、例えば以下のような形になります。
SDS法は、特にニュース記事や要点を早く伝えたい場合に有効です。
③AIDMAの法則
AIDMAの法則は、商品やサービスを販売する際に、消費者の購買行動を促すための心理的プロセスを示したマーケティングのフレームワークです。
特に、セールスライティングや広告製作において、効果的にアプローチするライティングの型として広く利用されています。
5つの英語の頭文字をとって、AIDMAと呼んでいます。
具体的には、以下の通り。
Attention (注意・注目・認知):
消費者の注意を引きつけ、商品やサービスの存在を認知させる。
Interest (興味・関心・好奇心):認知した商品やサービスに対して、消費者に具体的な興味や関心を抱かせる。
Desire (欲求・欲望・希望):その商品やサービスを「欲しい」「手に入れたい」という強い願望や欲求を消費者の心に喚起させる。
Memory (記憶・想起力):消費者の心に商品やサービス、あるいはその体験を強く印象づけ、購入時に思い出してもらえるよう記憶に残す。
Action (行動・購入):最終的に、「商品を購入する」「サービスに申し込む」「問い合わせをする」などの具体的な購買行動を促す。
AIDMAの法則を使って書く文章は、例えば以下のような形になります。
セールスライティングの際には、このポイントを意識して使ってみましょう。
忙しいあなたでも大丈夫!「10分写経」のすすめ


「写経が効果的なのは分かったけれど、毎日時間を取るのは難しい…」。と感じる方もいるでしょう。
私も最初はそうでした。
しかし、安心してください。
私は「毎朝10分」という時間を決めて、今年の1月1日から写経を継続しています。
この短時間写経こそが、忙しいWebライターが3日坊主に終わらずに済む最適な方法なのです。
この章では、10分間写経をおすすめする理由について紹介します。
なぜ10分でOK?短時間写経が良い4つの理由
1日10分という短時間でも写経が効果的であるのには、明確な理由があります。
それは、「集中力の維持」「習慣化のしやすさ」「他の作業との両立」「継続することによる効果」です。
4つの理由を次の節で、詳しく見ていきます。
①集中力の維持
人間の集中力は長く続きません。
特に慣れないうちは、長時間集中し続けるのは困難です。
しかし、10分という短い時間であれば、高い集中力を維持したまま取り組めるし、無理なく続けられます。
②継続しやすいからこそ成果につながる
毎日10分間だけの写経なら、無理なく続けられると思いませんか?
「ちょっとした空き時間」や「作業の合間」など、日々のルーティンに組み込みやすいのも10分間写経のメリットです。
毎日続けていたら、1年間で3650分。塵(ちり)も積もれば山となるですね。
この小さな積み重ねが、習慣化を後押しし、やがて大きな力へと変わっていくでしょう
③他の作業との両立
Webライターは執筆だけでなく、リサーチや構成作業、編集など、多岐にわたる業務をこなします。
10分写経なら、他のタスクを邪魔することなくスキルアップの時間も確保できるので、無理なく続けられます。
④継続することで最大の効果を生む
どんなに素晴らしいトレーニングでも、途中でやめてしまっては意味がありません。
毎日少しずつでも続けることで、着実に文章力が向上て、長期的な視点で見れば大きな成果につながるでしょう。
続けているうちに、「なんだか1日もやらない日があると気持ち悪い」と思えるようになったら、しめたものです。
「10分写経」の実践ステップ


では、具体的にどのように10分写経を進めていけば良いのでしょうか?
この章では10分写経の方法をステップ形式で取り上げたいと思います。
ステップ1:準備する~写経したい記事選び~
まずは、日々の写経で何を学びたいかの目的を明確にして、題材を選びます。
なにも決めずに漠然と書き写すだけでは、効果が半減してしまうからです。
写経の題材を選ぶ際には、下記の3つの点にポイントを置くと良いでしょう。
ポイント1 自分がよいと思った文章を選ぶ
写経のきっかけとなる文章は、単純にあなたが「良い文章だ」と感じるプロが書いた記事や信頼できるWebサイトを選びましょう。
コラム、エッセイ、評論などなど、自分が良いと思う文章であれば何でも可です。
ポイント2 構成がしっかりとしている文章を選ぶ
構成がしっかりしている記事は、Webライティングの基本を学ぶのに最適です。
写経する際には、情報がどのように整理され、読者に分かりやすく届けられているか論理の流れを意識しながら行うと効果的です。
これを意識すると、自分で複雑な内容のテーマを執筆する際に、整理して伝える力が養われます。
ポイント3 読みやすい日本語で書かれた文章を選ぶ
「長文でもスッと読める」と感じる記事を積極的に選びましょう。
一見すると当たり前のように思えるかもしれませんが、読者にストレスなく読ませる文章には、簡単に読めるようさまざまな工夫がされています。
例えば、「難しい漢字を使わない」「専門用語には説明を入れる」などです。
ステップ2:タイマーをセット!10分集中して書き写す
準備ができたらタイマーを10分にセットし、集中して写経スタートです。
写経する際には、文字数よりも質と継続を重視しましょう。
10分で何文字書けるかは人それぞれです。
写経する際には、構成や作者の意図を頭の片隅に置きながら進めていくことが大切です。
書き手の意図や工夫を推測しながら書き写すことで、より深い学びが得られるでしょう。
そして、10分経ったら、キリの良いところで一旦区切ります。
ステップ3:写経後の振り返りと学びのメモ
10分写経を終えたら、その日の学びを定着させるための振り返りの時間を取りましょう。
写経した文章を分析し、「ここが素晴らしい!」と感じた表現や構成、「ここは改善の余地があるかも」と感じた点を具体的に洗い出します。
なぜそう感じたのか言語化することで、自身のライティングに取り入れるべき点や注意すべき点が明確になります。
この積み重ねが、ライターとして大きな成長につながります。
その日の写経で学んだ表現や構成のヒントを、実際に自分のブログ記事やクライアントワークに活かすことも忘れずに。アウトプットをすることで、知識は定着していきますからね。
写経で得たスキルを最大限に活かすWebライターとしての次の一歩


写経で得た文章の知識。
せっかく学んだのに、そのままにするのはもったいない。
ほかのライターが書いた文章のコツを実際のWebライティングの現場で最大限に活かすためにも、さらに以下のステップを踏んでいきましょう。
この章では、写経でさらにライターとしての文章力を挙げるためのポイントを紹介します。
読者ファーストの文章を書く意識を持つ
Webライティングの究極の目的は、読者の抱える疑問や悩みを解決して価値を提供することです。
常に「読者は何を求めているのか?」「どうすれば読者の役に立てるか?」という視点を忘れずに記事を書く姿勢が求められます。
写経で得た知識を、「読者ファースト」の視点をもつきっかけとして活用しましょう。
最初に構成を作る習慣で効率UP
写経を通じて、優れた文章の構成や論理展開を学んだら、記事作成に積極的に応用していきましょう。
「最初に構成を作れば文章を書きやすい!」
これは、多くのプロが実践するテクニックです。
構成の作成は、記事という建物を作る際の「設計図」に他なりません。
この設計図を先に描くことで、執筆中に方向性を見失わずに記事を作成できます。
また、構成を先に作っておくことで、一貫性があり、読者に伝わる記事をスムーズに書き進めることができるでしょう。
ちなみに、私が実践している構成作りの手順は、以下の通りです。
まずは、自分が書こうとしているテーマについて信頼できる複数のサイトを読み込み、基本的な知識やトレンドを把握します。
そのテーマ(キーワード)で検索する読者が、一体何を知りたくて検索しているのか、どんな悩みを解決したいのかを具体的に想像します。
そのキーワードで上位表示されている競合記事が、どのような検索意図に基づいて、どのような構成で書かれているかを詳細に分析します。
検索結果に出てくる関連キーワードを調べ、読者が次に知りたい情報や記事に含めるべき内容を洗い出します。
これらの調査結果をもとに、自分なりの視点や深掘りした情報を取り入れて独自の構成を作ります。
このように、記事の全体像を先に決めて執筆を進めることで、記事を書いている最中に迷うことが減り、一貫性のある記事を書けるようになります。
つまりは、読者の心に響く質の高い記事を効率的に作成できるというわけです。
Webライターとしての情報と学びを発信する
スキルアップに終わりはありません。
写経で得た知識を活かし、常に学び続ける姿勢がWebライターとして成長する鍵です。
クライアントワークだけでなく、ほかの方法で情報発信を続けることで、途切れることなく自分の文章を高めることにつながります。
例えば、以下のような方法で発信をするのはどうでしょうか?
ブログを立ち上げて記事を書く
自分のブログは、学んだことをアウトプットして読者の反応を直接感じられる最高の練習の場です。
ブログを立ち上げて、どんどん文章を発信していきましょう。
noteに記事を書く
noteはブログよりも手軽に始められ、専門的な知識がなくてもすぐに記事を公開できるプラットフォームです。
Webライティングの学びや気づき、案件で得たノウハウなどを発信することで、自身の専門性をアピールしていきましょう。
X(旧Twitter)で情報発信し続ける
Xは、短い文章で要点を伝える練習になり、他のライターとの交流や情報収集の場にもなります。
こちらもどんどん発信していきましょう。
webライターは写経をやろう!あなたのWebライティングスキルは飛躍的に向上する
Webライティングのスキルを効率的に向上させるための「写経」は、忙しいあなたでも1日10分から始められる効果的なトレーニングです。
- 写経は、文章の「型」や多様な表現を身体で覚える効果的な方法
- 書き手の意図や読者の心理、文章の構成を深く分析する力が養われる
- タイピング速度と正確性も向上し、作業効率アップにもつながる
- 写経で得た知識をアウトプットするとさらに効果的!
これらの学びと実践を踏まえて、今日からぜひ「10分写経」をあなたの習慣に取り入れてみてください。
写経を継続することこそが、Webライターとしてのあなたの文章力を飛躍的に向上させ、より多くの読者に価値を届けられるようになる確実な一歩となるでしょう。
さあ、今すぐあなたの文章力を磨き始める第一歩を踏み出しましょう!
私もこれからやろうと思います!
にほんブログ村




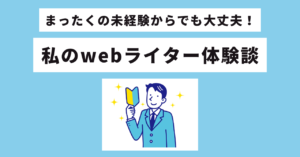


コメント